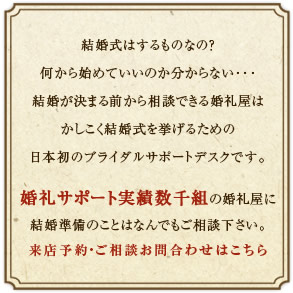白無垢は儀式の衣

日本女性の挙式でのみ着る事が許される儀式の衣裳です。
掛下から小物類まですべて純白で揃えられ、頭には綿帽子か角隠しを付けます。
いつの頃から礼装の支度として始まっているのかは、はっきりしませんが白無垢の花嫁の凛とした姿は、お嫁入りの自分のけじめの衣裳として選ばれる方が増えていらっしゃる事は、嬉しい事です。
白は清浄を表します。嫁としては婚家の色にあらためて染まって行きますとの覚悟も表しているとも言われます。
花嫁様の小物には
1)「はこせこ」襟元に納められた小物入れ
鏡や懐紙など化粧ポーチのような使い方になりますが、昔は長期間の移動で嫁入りなどもあり母親が娘のために薬なども忍ばせたとも言われています。
2)「懐剣」胸元の帯におさめられています。
護身用として所持する短刀が納められています。道中の身を守るようにとここにも母の思いが込められています。
3)「扇子」末広とも呼ばれ手に持たれます。
要から広がっていく末広がりがおめでたいとされ、和装の正装では必ず持ち礼儀にあわせて当日使用します。
4)帯揚げ・帯締め
帯を結ぶときの実用品として用意されているものですが、花嫁衣裳では華やかな飾りとしての用途としても担ってます。
5)「抱え帯」かかえおび
着物をお引きで来付けている時に、外出する時引きずってしまうので腰のところでたぐって抱え帯を使用します。今は実用で使用せずお太鼓の左下で結んで後ろ姿の飾りとして使われます。

日本の花嫁の衣裳に十二一重など幾重にも重ねることが多いのは、おめでたい事は何度も繰り返して欲しいとの願いも込められている。そう言われると重い衣裳も身に着ける思いとして頑張れますね。
昔は実家の家紋をつけた白無垢で婚礼に臨み、宴では嫁入り先の家紋をつけた衣裳に着替えた事から、花嫁のお色直しがはじまったと言われます。
北陸地方ではその名残か、新郎側より花嫁へ新郎側の家紋のついた留袖を贈る風習がございます。その留袖にあう帯を花嫁の母が選んで嫁入り支度に持たせます。
両家の結びつきを育むひとつの方法だったのでは無いでしょうか。ご披露宴でのお色直しにそのお留袖と帯をあわせてお召しになる花嫁様が多かったです。25年前のお話ですよ。